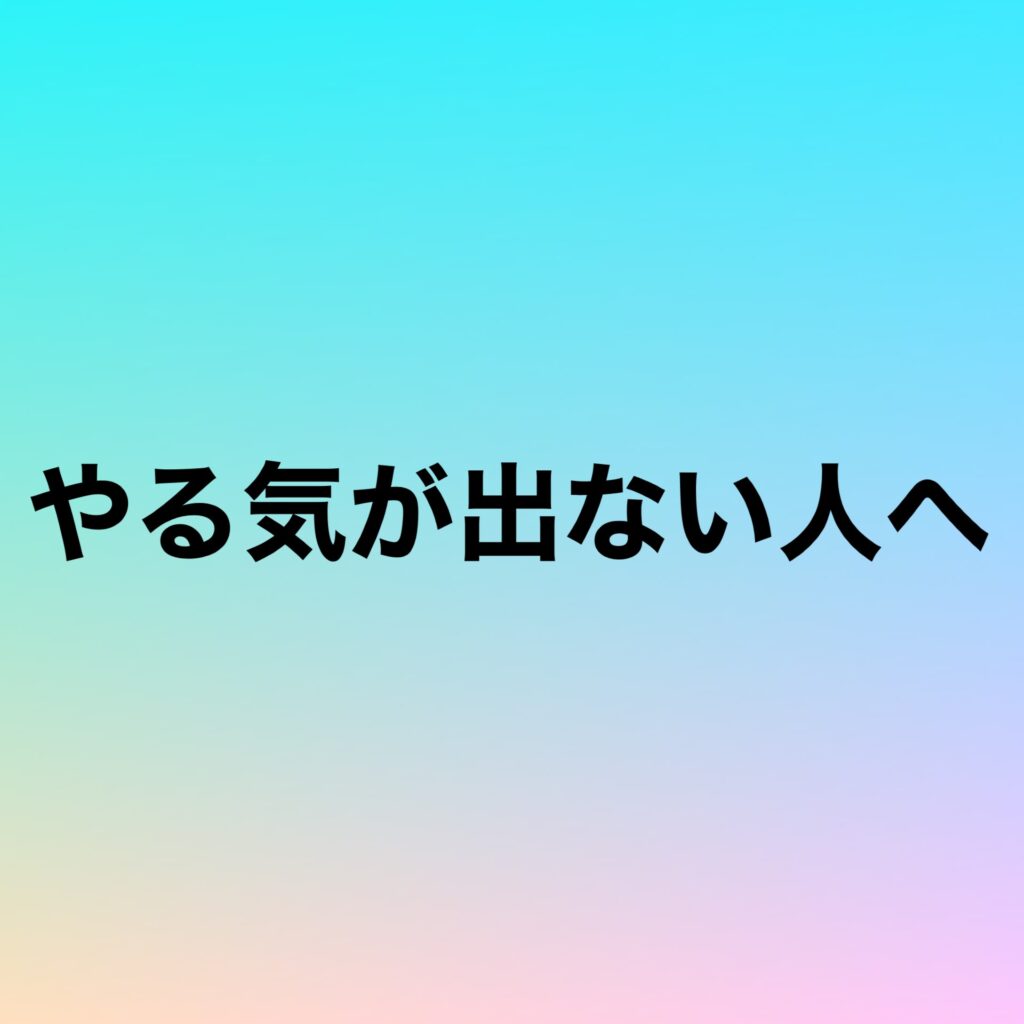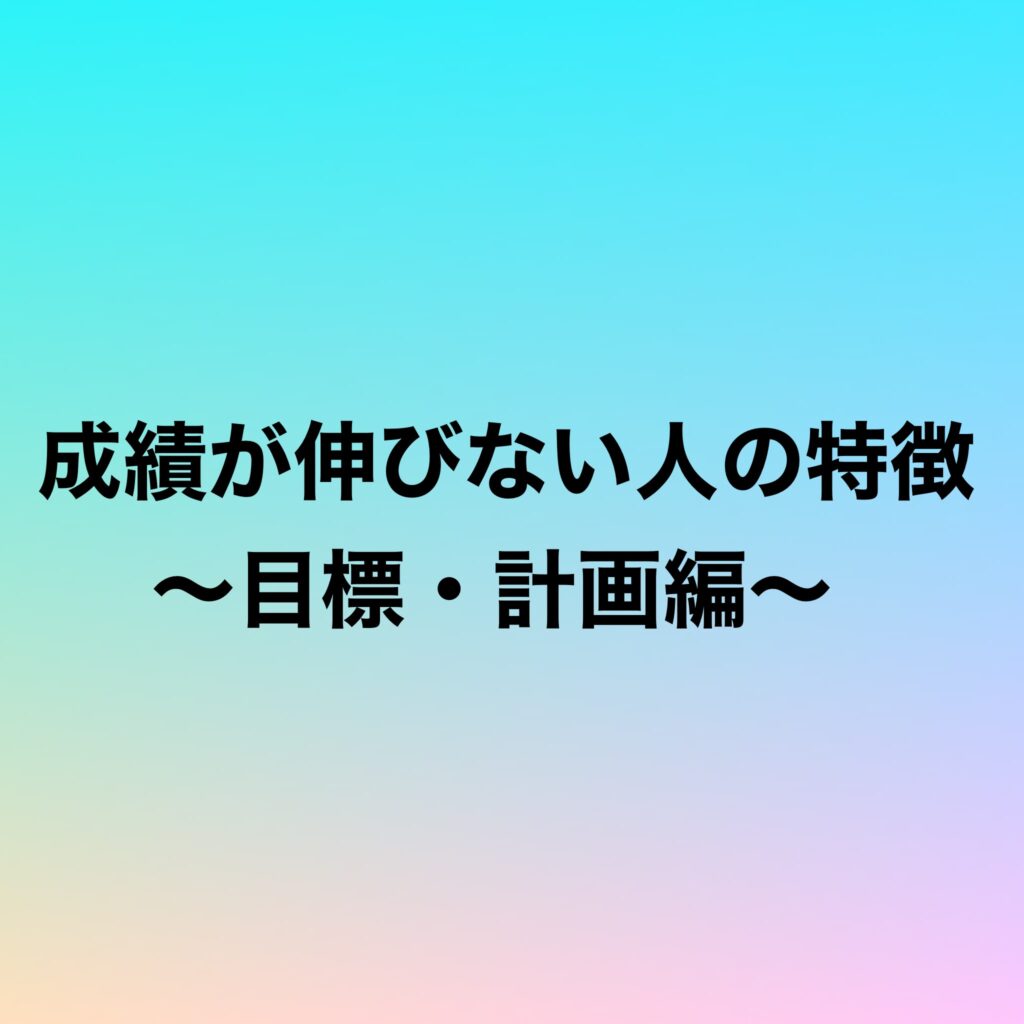皆さんは『学習性無力感』という言葉を知っていますか?
僕がこれに関する記事を読んだのは、ジュリアス・シーガル著『生きぬく力』(小此木啓吾訳 フォーユー 1987)という本の中でした。
この言葉を検索すると、詳しい説明が出ていたので、少し長くなりますが、まずはそれを一部ここに引用させてもらいます。これはWikipediaからのものです。
・学習性無力感 learned helplessness
学習性無力感(がくしゅうせいむりょくかん、: Learned helplessness)とは、長期にわたってストレスの回避困難な環境に置かれた人や動物は、その状況から逃れようとする努力すら行わなくなるという現象である。
なぜ罰されるのか分からない(つまり非随伴的な)刺激が与えられる環境によって、「何をやっても無駄だ」という認知を形成した場合に、学習に基づく無力感が生じ、それはうつ病に類似した症状を呈する。1967年にマーティン・セリグマンらのオペラント条件づけによる動物実験での観察に基づいて提唱され、1980年代にはうつ病の無力感モデルを形成した。心理学者のマーティン・セリグマンが、1960年代にリチャード・ソロモンの元で学生生活をしていた時期に思いつき、それ以来10年間近くの研究をもとに発表した。抵抗や回避の困難なストレスと抑圧の下に置かれた犬は、その状況から「何をしても意味がない」ということを学習し、逃れようとする努力すら行わなくなるというものである。
学習性無力感は、1967年にセリグマンとマイヤーが犬に対して条件付けを用いて行った研究によって提唱された。また別の1967年の論文の、実験の内容は以下である。
犬を以下の3つの群に分け、オペラント条件づけに従って、電撃回避学習を課した。
- 頭部を動かすと電撃を停止できる群。
- 第一統制群:パートナーが受ける電撃を同様に受ける。
- 第二統制群:電撃を受けない。
第一統制群の、自分では電撃を停止できない犬は、回避行動をとらず、電撃を受け続けた。こうした実験によって非随伴的な刺激が与えられる環境によって、何をやっても無駄だ、統制不能だという認知を形成した場合に、学習に基づく無力感が生じるとし、学習性無力感が提唱されたのである。
続いて、サカナ、ネズミ、ネコ、サル、ヒトでも、適応的な反応を起こさなくすることが、実験にて観察され、その学習性無力感の症状が、うつ病の症状に類似しているとされた。
セリグマンは、1975年には、人間も加えた研究を加えて、うつ病の無力感モデルの理論的な基礎を形成し、1980年代にはその治療や予防に関しても、学習性無力感とうつ病とで比較し、それら二項間における内容はほぼ同様である。
長期に渡り、人が監禁されたり、暴力を振るわれたり、自分の尊厳や価値がふみにじられる(主として、いじめやモラルハラスメントに代表される人格否定)場面に置かれた場合、次のような徴候が現れるという。
- 被験者は、その圧倒的に不愉快なストレスが加えられる状況から、自ら積極的に抜け出そうとする努力をしなくなる。
- 実際のところ、すこしばかりの努力をすれば、その状況から抜け出すのに成功する可能性があったとしても、努力すれば成功するかもしれないという事すら考えられなくなる(言い換えると、長年受けた仕打ちによる反動で、どんな可能性さえも「無駄な努力」と断じ、自発的行動を全くしなくなる)。
- ストレスが加えられる状況、又ストレッサーに対して何も出来ない、何も功を奏しない、苦痛、ストレス、ストレッサーから逃れられないという状況の中で、情緒的に混乱をきたす。
人の行動は、良かれ悪しかれ何らかの学習の成果として現れてくるものである、という学習理論を土台とした理論である。拉致監禁の被害者や長期の家庭内虐待の被害者、学校での学歴信仰やいじめ、会社などでのモラルハラスメントや、いわゆるブラック企業に雇用され低賃金で過酷な労働を強いられ続けながらも自ら進んで退職しない者が一定数居ることなど、行動の心理的根拠を説明する理論として、注目されている。
Wikipedia
どうですか、なかなかに興味深い話でしょう?
僕は宮崎の公立普通科高校のありようを何度も批判していますが、それがこれまで変えられずに来たのは、他のありようを知らないので、「これがふつう」と思い込んでいる生徒や親が少なくないということの他に、この「学習性無力感」も関係しているのではないかと感じたのです。
何を言っても変わらない、ならばひたすら我慢して、三年間をやり過ごすしかない。
そう考えるようになってしまうのです。
そのような思いを抱く人が支配的になると、そうでない生徒や親、あるいはこれではまずいと考える先生がたまにいて、行動を起こそうとしても、誰も協力してくれず、孤立させられてしまう。
そうなると今度はその人も、「やっぱり駄目なんだ」と「無力」を“学習”してしまうのです。
これは伝統的に独裁者や、地域・集団・家庭の小暴君が用いてきた支配のテクニックでもあります。
反抗者が出てくると、これを徹底的に弾圧し、「オレに逆らうとこういう目に遭うぞ」という見せしめにする。
その人が痛い目に遭わされるだけで、決して何も変わらないことが示されるのです。
そういうことが繰り返されると、やがて誰もが「やっぱり無駄なんだ」と無力感による服従を学習し、抵抗する人間はいなくなってしまうのです。
そういうことはどこでも起きる可能性がありますが、とりわけ日本社会ではこれは起きやすいことです。
理由は、日本人の特性として、「世間」というものが大きな力をもっているからです。
そのため大勢順応志向が強く、よかろうと悪かろうと、「他と違う」ことをするのを恐れるようになる。
この「世間」は、誰か特定の人間が支配しているものではありません。
一種の「共同幻想」みたいなものですが、日本人は何よりそれを恐れるのです。
だから、ある子供が、家に帰って、「もうこういう学校には耐えられない」と親に訴えたとします。すると親はこうたずねるのです。
「他の子たちはどうしているのか?」と。
「わからないけど、みんな我慢してるんじゃない」
「だったら、おまえにだけそれができないというのはおかしいんじゃないのか? 今まで何年も、何十年もそれが行なわれてきて、みんながそれを受け入れて、耐えてきたというからには、そこには正当な理由があるはずで、おまえだけそれはイヤだというのは、おまえが弱すぎるか、わがまますぎるからではないのか? おまえは人並のことがどうしてできないんだ?」
全く不合理な、愚劣なことが何年も、何十年も続けられるというのは、神ならぬ人間がつくるこの世界では別に珍しくないことですが、多くの日本人にとっては「世間並(皆がすること)」は正義かそれに類したものなので、そのように言われると反論が難しいのです。
そうしてそう言われると、その子は「人並のことすらできない」自分に劣等感を覚え、それがおかしいと感じる自分の感受性それ自体を疑い始めます。
そのように仕向けるのは、人から自信を奪って服従させるのには最も効果的な心理テクニックなのですが、親は意図せずわが子に対してそれをやってしまうのです。
その影響はかなり深刻です。
自分の感受性に対する信頼感を失った人間は必然的に神経症的になり、強い不安から、自分がすがるべき権威を、従うべき判断基準をたえず外部に探し求めるようになるからです。
彼または彼女はつねにより強力な権威を、より多数の支持を求めて右顧左眄(うこさべん)するようになり、そうした混乱の中で、自分が何を感じているのかということさえ、しまいにはわからなくなってしまうのです。
これは親子間だけの話ではなく、日本の社会というのは今でもそうなのです。
技術者やタレントなど、海外、とりわけ西洋で評価され、有名になると、とたんに国内の評価まで変わってしまうのです。
以前は無視していたり、ボロクソ言っていた人たちが、いつの間にか「素晴らしい」と賞賛するようになっている。
誰も、「あんた、この前まで言っていたことと全然違うじゃないか」と咎め立てたりはしない。
自分も同じだからです。
政治家や実業家、文化人なんかも、途中まで絶賛されていたのが、何かの容疑で警察の捜索を受けたとか、スキャンダルで週刊誌沙汰になったりすると、マスコミは今度は手の平を返したみたいに一斉に攻撃するようになりますが、それも同じです。
中には記者がわざわざテレビに出て、「ずいぶん前からおかしいという情報はあって、私たちもそれはすでに把握していました」なんて自慢げに言うのですが、だったら何でそのとき取材して報道しなかったのかとは、誰も言わないのです。
「堕ちた権力」ならいくら叩いても安心だが、「世間」を味方につけているときにそんなことをするのは危険だと、いかにも日本人らしくそう思うのでしょうか。
実に頼りになる人たちです。
だから、「皆がそうしている」とか、それに従っているというのは、別にそれが正当だとか立派だとかいうことの証拠には全然ならないのですが、早くから見えない「世間の目」というものの圧力にさらされてきた日本人には、どんなことであれ多数が従っていることを変えるというのは大変なのです。
大人たちが会社や職場についてあれこれ愚痴をこぼしているときも、聞いているといかにも馬鹿馬鹿しいことが行なわれているようなので、「そんなもの、さっさと変えてしまえばいいじゃありませんか?」と言うと、「いや、事はそうかんたんじゃないんです」と、変えられない理由を滔々と述べ出したりするので、「この人は一体何を言いたいのだ?」と不思議に思うことがあります。
だって、それがイヤで、不快で、会社なり組織なりの機能がそれで深刻に害されていることもわかっているのでしょう?
そして、多くの場合は、どういうふうに変えてゆけばいいのかという、その方向性もわかっているわけです。
だったら愚痴ばかり並べて、いつまでも我慢してストレスを募らせていないで、さっさと行動すればいいわけです。
その際、多少の摩擦や対立が起き、波風が立つのはやむを得ない。
これはいたってロジカルな話ですが、そう言うと、「いや、それはわかっているんですが…」とまた言うのです。
あたかも「情念」がそれに抵抗するとでも言うみたいに。
実際に、この場合は「情念」が抵抗しているのです。
それは子供時代から受けてきたマイナスの条件づけが無意識にしみわたっていて、恐怖感情がそこに「対立」や「孤立」のにおいをかぎつけ、からだも頭も動かなくなってしまうからです。
そうなると思いつくのは「何もしない」ことを正当化する理屈ばかりになってしまう。
「学習性無力感」がその背後にあるわけです。
学校は「伝統」だというので毎日の課外を維持し、さらに進学率が高くなる中、とにかく大学進学実績を上げねばならないと、罰則の類で脅しながら宿題を増やし、長期休暇中の課外授業の時間数も増やして、生徒側の消化能力や負担の大きさは考えずに「拡大」路線をひたすら邁進し、そうした中でどんどんわが子の元気がなくなっていくのを見る親たちは、もう少し子供の全体的な成長や健康に配慮した教育をやってもらいたいと思いながらも、「専門家ではない」ので注文はつけにくいということで沈黙を守り、生徒たちは生徒たちで、協力・団結の精神や覇気に乏しく、ほとんど抵抗もできないまま締め付けの強化に身を任せて苦しむ―。
そういう図式のようなものができてしまっているのではないか、ということです。
僕は、最大の要因は「学校側の独善性」にあると思うのですが、先生たちもそれを“主体的に”推進しているようには見えないので、敷かれたレールの上を走っているうちに、ブレーキをかける者もいないまま、だんだんそれがエスカレートして、こうなってしまった、というようなところが強いように思えるのです。
ひょっとしたらこれは、それに関係する人たち皆が多かれ少なかれ「学習性無力感」の中にいるということなのではないでしょうか?
その結果ひき起こされる問題点の一つに、「環境に対する積極的・自発的な働きかけが起こらなくなる」ということが挙げられていましたが、生徒や保護者たちが「忍従」しているというだけでなく、学校の先生たちも既成のレールの上をひたすら走り続けることしか知らないように見えるからです。
しかし、教育のみならず、ビジネスでも学問研究でも、スポーツの類でも、それは同じですが、自発性や主体性を欠いて成功するようなものは何一つありません。
短期的には頭ごなしの管理的なスパルタ指導が大きな成果を上げることはありますが、その寿命は短く、しばらくすればそれは主体性・自発性を奪われたことによる無気力によってマイナスの埋め合わせを余儀なくされるのです。
過度な管理教育は、受験のようなことにおいてすら、生徒の自発性・主体性を尊重する教育に結局は負けてしまうでしょう。
それを私たち大人はよく認識すべきではないでしょうか。
今は羅針盤のない困難な時代で、これを突破するには創造的で柔軟な発想のできる、パイオニア精神と行動力に富む若者を育てるしか方法はないと思われます。
今の過ぎた管理教育でそのような人材が育つと考える人はたぶん一人もいないと思うので、関係者各位はよくよくお考えいただきたいと思うのです。