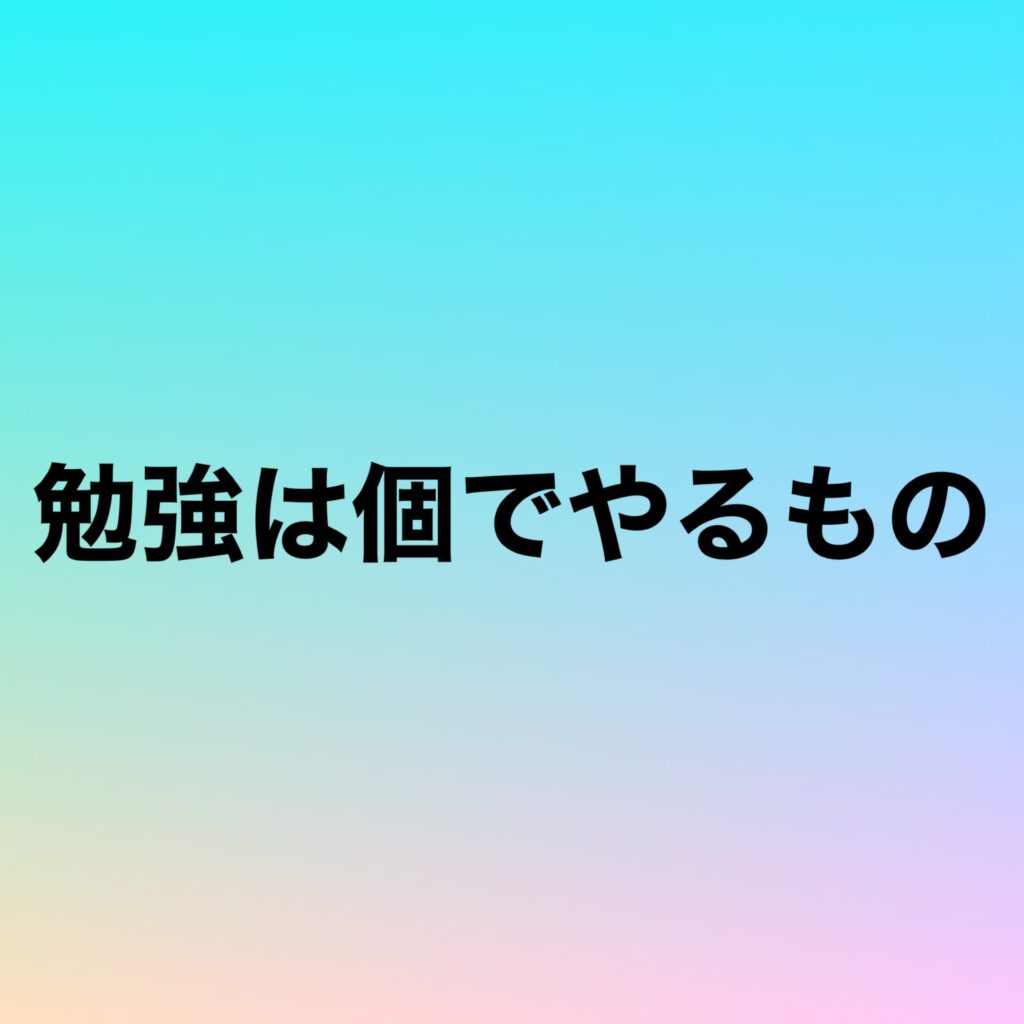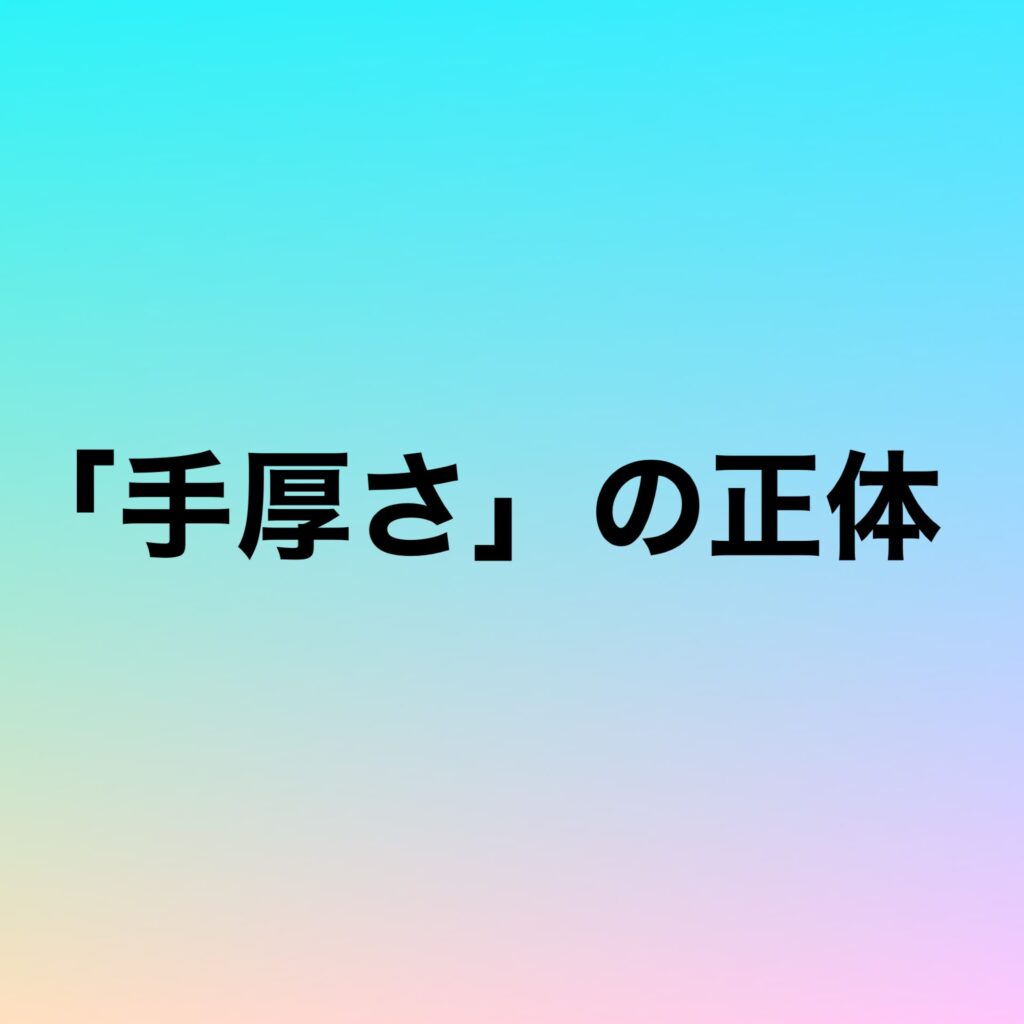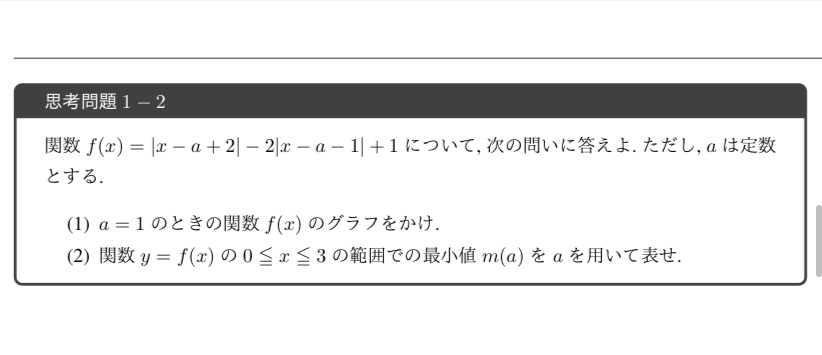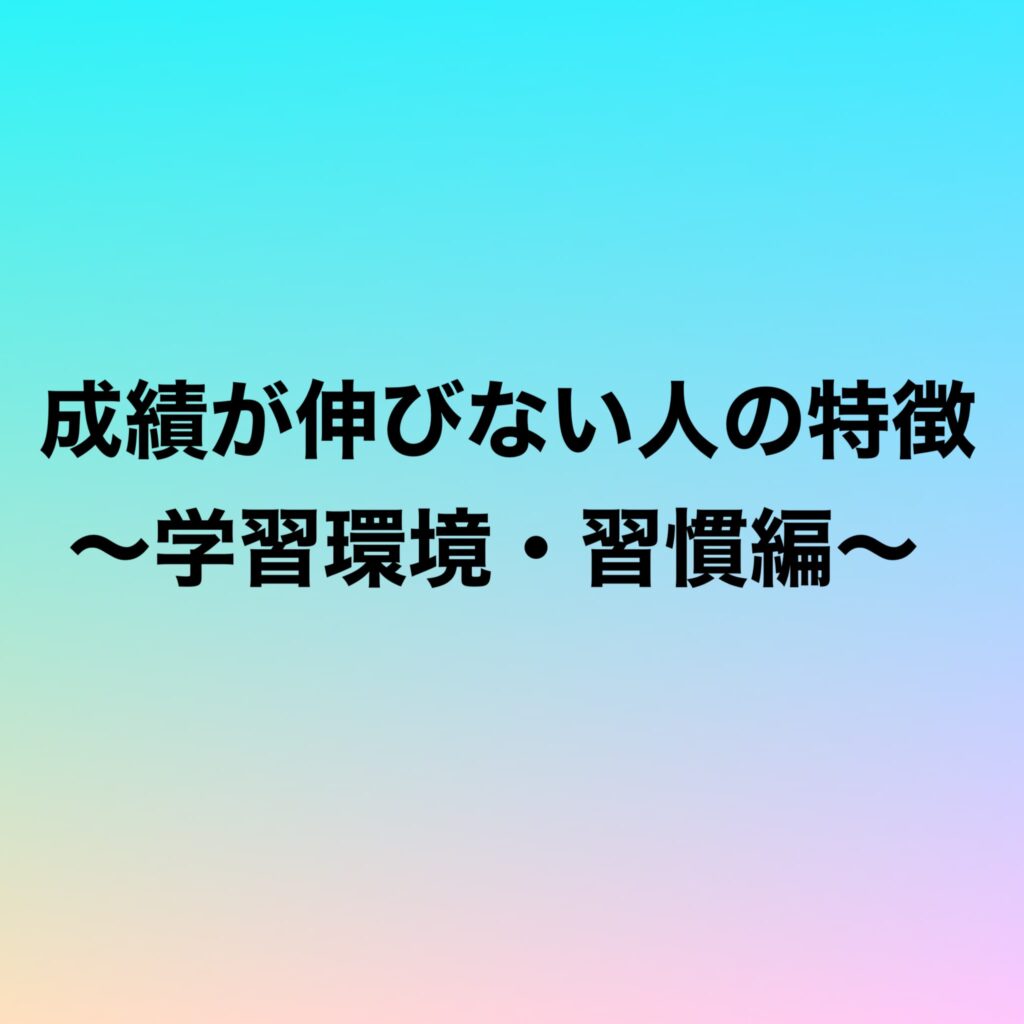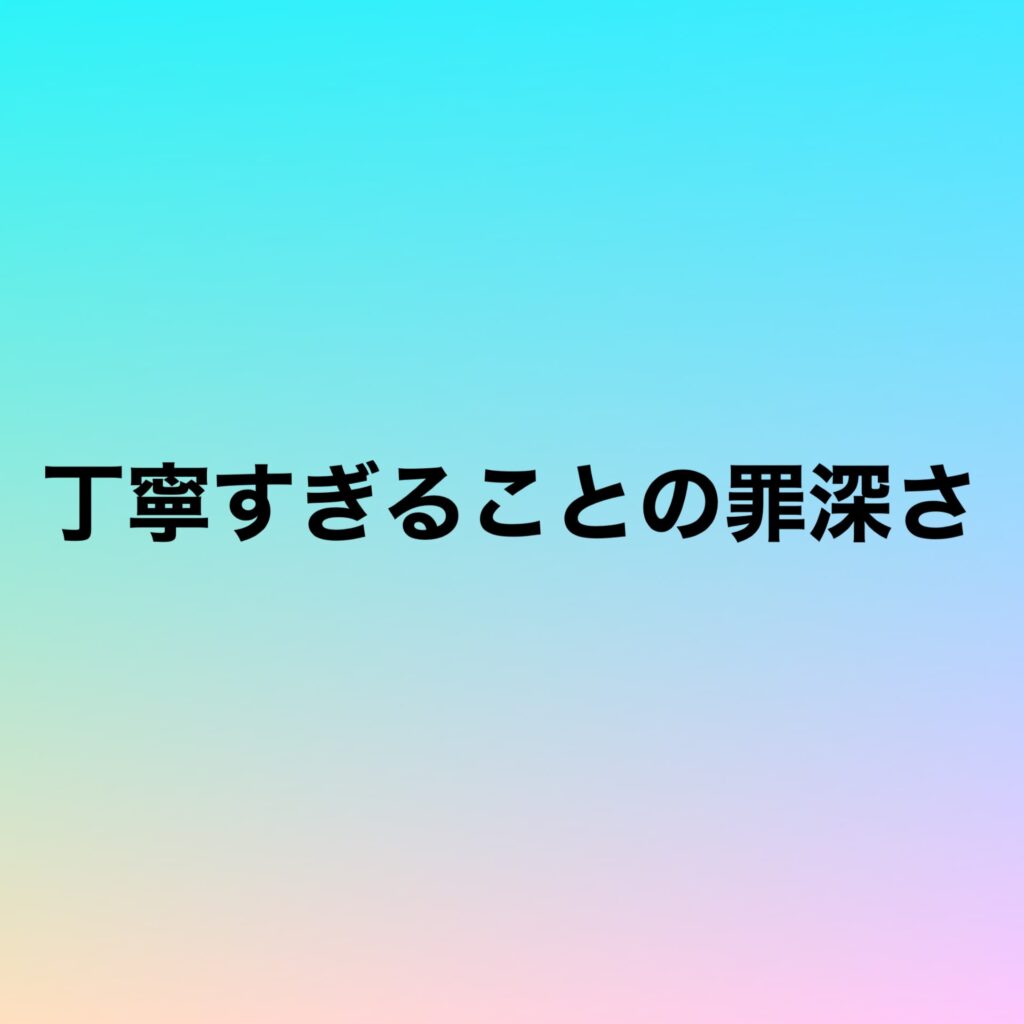僕はここ数年、「MOBA(Multiplayer Online Battle Arena)」と呼ばれるジャンルのゲームにはまっており、よく遊んでいます。これは簡単に言えば5対5の陣取りゲームで、試合に勝てば自分のレートが上がっていき、よりハイレベルな相手と当たっていくというようなシステムになっています。このゲーム、結構難しくて、平均勝率は大体55%前後と言われていますが、中には勝率80%を超えるような猛者も少なからず存在します。
さて、このゲームはチーム戦なので、ゲームをしているとしばしば試合中や試合後にこのようなことを言っている人たちを見かけます。
「(俺はまともなのに)味方がくそだ!!!!!!!」
そして、こういうことを言っている人に限って勝率を見てみるとたいてい5割弱ぐらいなものです。
人の自己評価というものは、他人による客観評価よりも高くなる傾向があり、平均的には周囲の評価よりも20%上乗せして評価すると言われています。この効果を、心理学では平均以上効果と呼びます。
主に味方のせいにするプレイヤーは、自分の実力が現レートに見合ってないと認識しています。特にMOBAは人に責任をなすりつける事が容易でもありますので、このような発言がよくみられるわけです。
また、これは逃避行動の一種でもあります。彼らの思考回路は大体次のようなものです。
- 試合に負ける
- 俺に落ち度はあったのか?(ストレス1)
- ないよなあ?(ストレス2)
- じゃあなんで負けたんだよ!
- 味方がごみだったからだわ!(ストレス解消)
人というのは、自分に否があると認める行為に対して多大なストレスを感じます。
脳はストレスが大嫌いなので、できる限り自分の否を認めるのを避けようとします。これは私達人間が持つ防衛機能でもあります。
勝てないプレイヤーは自分の実力がレート帯相応だという事を認めず、自分を周囲に比べて平均以上だと思い込むことによって、自尊心を守り、ストレスを緩和しようとします。
しかし、平均以上効果が強いプレイヤーは、成長しません。
負け試合を振り返る時、試合の敗因は常に自分を軸に考えないと次の試合の勝利には関わってきません。まずは素直に負けを認めましょう。大切なのは振り返りを行い、次の勝利への可能性を検討する行動です。
自分の動きに一切の落ち度がなかったと考えた瞬間、振り返りは行われません。
平均以上効果による感覚の麻痺を避け、謙虚な姿勢を持ち、自分を変えるための行動を起こすことがMOBAにおいて勝率を上げることには必要なのです。
そしてここからが本題。これはまさに勉強でも言えることです。勉強においても成績が伸びない人の特徴として次のようなことがよく見受けられます。
- 人のアドバイスに耳を傾けない
たとえば「英語を基礎から勉強するように」と言われても、「基礎の部分なんかいまさらやったって、成績は上がらないだろ」と反発する。「復習が疎かになっているから新しい参考書に手を出すのをやめなさい」と言われても「どんどん新しい参考書をやっていかないと合格できないだろう」と無視する。現状が良くないのにもかかわらず勉強法について、先生からの意見をほとんど受け入れない人。
「自分のことは、自分がいちばんわかっている」「今の自分の勉強法が、自分にいちばん合っているんだ」と、成績がなかなか上がらなくても先生からの意見に耳を貸さない人です。
- 自分の欠点に向き合えない
複数の模試を受けると、調子が良くてA判定を取れることもあれば、調子が悪くてD判定になってしまうこともあります。そんなとき、伸びない人はよく次のように考えます。
「今回は問題が難しすぎだわ」
「ここは将来使わないから点数なしでもいいわ」
「D判定のほうは、ケアレスミスが多かった」
そして「自分の本当の実力はA判定だ」と言い聞かせてしまうのです。
自分の勉強法が正しいと信じて疑わず、先生の意見を聞き入れない人。悪い結果と向き合わず、自分にとって都合のいい結果だけを見てしまう人。
先生の教える勉強法はたしかに、その生徒に合っているものではないのかもしれない。でも、「合っていない」という保証だってありません。部分的にでも取り入れてみる価値はあるはずです。
D判定だったのは、本当に「ケアレスミス」のせいだったのかもしれません。しかし、「ケアレスミス」だと決めつけないで、十中八九、本番でも同じように「ケアレスミス」をします。
「ケアレスミス」という言葉は、「そのときは不注意のせいで間違えてしまったけど、次に同じ問題が出たら多分正解できる、取るに足らないミス」という意味で使われますが、難関大合格者の中で「ケアレスミス」という言葉を使う人はすごく少ないです。彼らにとって、「ケアレスミス」なんて存在しないのです。
間違ったのなら、なんらかの理由があるはず。時間が足りなくて不注意になってしまったのならもっと時間に余裕ができるように修正するべきですし、時間があったのに間違えたのなら演算規則の理解が足りていない、なんらかの知識をど忘れしているなどの原因が考えられるのでその単元を復習するべきです。
そうやって、自分のミスとしっかり向き合って、次に活かそうとする。だから彼ら彼女らは「ケアレスミス」という言葉は使わないのです。
「ケアレスミス」という言葉1つとっても、成績を上げられる性格か否かがはっきりわかれるんです。きちんと自分の失敗から学ぼうとすれば、もしかしたら自分の弱点克服につながったかもしれません。
どんなに受け入れ難いことでも、一度きちんとその意見を聞き、受け入れる。受け入れ難いことでも、一度は実践してみて、それから判断する。そういう、いい意味での「素直さ」「謙虚さ」が欠けてはいませんか?
自分が謙虚でないうちは、なかなか「謙虚さ」を欠いていることに気付けません。心理学的効果が成績の向上を阻害していても、自分ではなかなかそれに気がつけないし、人から指摘されても、受け入れられない。これが、「不合格」になる最たる原因なんです。
逆にいうと、どんな勉強をしている場合でも、どんなに勉強法に欠点がある人でも、「周りのことを否定するのではなく、一度肯定してみる」「人からの指摘を受け入れられる」というマインドさえあれば、成績を向上させることが可能です。なぜならそういう人は、勉強に対してPDCAを回せるからです。
「一度プランを立てて行動してみて、その行動をチェックした後に改善してみる」、というビジネスでよく聞くこのPDCAですが、自分の勉強に対してPDCAを回せる人は強いです。考えた勉強法を実践してみて、そのダメなところをチェックし、修正してもう一度やってみる。こうやって、自分の勉強の精度をどんどん上げていくことができる受験生というのは絶対に成績が上がります。
そして、ここでいちばん大変なのが「チェック」です。「自分の勉強のダメなところ」を受け入れる「謙虚さ」がないと、「チェック」ができないのです。自分で自分の悪いところを見つける場合もあるでしょうし、誰かから指摘されることもあるでしょう。しかしどちらにしても、「謙虚さ」を欠いていると「自分の悪いところ」を受け入れられません。ここで立ち止まってしまう人が非常に多いのです。
「勉強した内容が再現できるか?」というチェックや、「勉強して成績が上がるのか?」というチェック、「自分の知識として使えるようになっているか?」というチェック。たくさんチェックするべき項目はあります。しかし「謙虚」でないと、チェックを怠ってしまい、いつまでたっても成績が上がらない。成績向上のボトルネックは、上にあげたような心理学的効果なんです。
これは何も勉強だけに留まる話ではありません。人からの指摘を真摯に受け入れて、自分でPDCAをうまく回せるようになると、どんな分野でも活躍できるようになる、というのは本当に多くのビジネス書で語られていることです。
自戒の意味も込めて、この記事を書きました。